 
第4話(その1)
4
「バルディアス方面に、友軍と帝国軍の戦力が集中しつつあります。妨害電波、反重力磁場の影響で詳細はわかりかねますが、戦端が開かれるのは時間の問題かと」
クレティナス王国軍第四四艦隊の司令官グランビル少将は、艦隊旗艦サラマンダーの艦橋で副官の報告を聞いていた。アルフリートが新設された自由艦隊(第四九艦隊)の司令官に任命されたことに伴って、新しく第四四艦隊の司令官に就任した青年将校である。彼は貴族階級の出身ではあったが、アルフリートと同じ普通の士官学校に通った変り者で、アルフリートの数少ない友人の一人であった。「時間がない。急ぐぞ。戦いが始まる前に『赤の飛龍』に合流するんだ」
グランビルは、王国軍司令長官ベルトール元帥から直接バルディアス方面で戦っているアルフリートの援護をするように命じられていた。ベルトール元帥がアルフリートの自由艦隊に初戦を勝利で飾ってやりたいと思ったのが主な理由であったが、グランビル自身が彼とともに戦いたいと主張したことも一つの要因となっていた。グランビルの率いるこの四四艦隊は、つい半年前まではアルフリートが指揮していた艦隊である。将兵たちはかつての司令官の恩に応えようと意気が盛んであった。
「バルディアスの門」の周辺にアルフリートの指揮する第四九艦隊が姿を見せていた。総数一○○○隻の艦隊のうち、三○○隻が欠けた七○○隻の艦艇が陣形を整えている。残りの三○○隻は別働隊として一○○隻ずつ三つの部隊に分かれて、それぞれがヴィストゥール要塞で受け取った推進装置つきの小惑星を運んでいた。
アルフリートの「バルディアスの門」攻略の作戦は、簡単に言って、三個の小惑星を三つの要塞にぶつけると言うものであった。そのために、ベルソリック、グエンカラー、ブラゼッティと言った分艦隊司令官に小惑星移動の任務を与え、アルフリートの本隊は、敵の目をそらす目的で囮となって正面からタイラーに挑むことになった。
標準暦一月二二日一三時。
宇宙要塞「バルディアスの門」に敵の来襲に備えて待機していたユークリッド・タイラーは、アルフリート・クラインの到来を知った。要塞周囲に宙域警戒の目的で配置していた一万個の索敵衛星の一つが、星の海を背景に接近してくる無数の光点の映像を送信してきたのである。
「『赤の飛龍』の登場か。さて、彼はどう出てくるのかな?」
誰に尋ねるのでもなく、タイラーは呟いた。退屈な時間が終わりを告げ、脳細胞が活発なダンスを踊り始める。
「距離はどのくらいだ。情報士官、時間的距離で報告しろ」
「480光秒、およそ四時間の距離です」
瞬時にコンピューターで計算され報告される。
「敵の数は判るか」
「詳細は判りかねますが、通常の一個艦隊、五○○隻以上はあるものと思われます」
「了解した。ただちに、第七艦隊と第一九艦隊、全艦隊を出撃させる。通信士官、要塞内に警報を鳴らせろ。クレティナス艦隊、来襲と」
タイラーは叫んだ。
要塞内に警報が流れ、兵士たちの動きがせわしくなる。まず、老練な用兵で知られるオーエン・ラルツ中将の第一九艦隊が、要塞「ウルド」から出撃し、数分おいて、神将タイラー率いる第七艦隊が、要塞「スクルド」から出撃した。
要塞「バルディアスの門」を構成する三つの要塞「ウルド・ベルダンディ・スクルド」から発進した帝国艦隊は、計一四○○隻である。総司令官タイラーの考えは、敵の出方を待ってそれに応じる作戦であったため、艦隊は要塞からそれほど距離を置かない宙域で前進を止め、そこに布陣した。
一方、アルフリート・クライン率いるクレティナス第四九艦隊七○○隻は、帝国艦隊に二○光秒(およそ一○分)の距離を置いて凸陣形を敷いて布陣した。帝国艦隊に数的には及ばないものの、隙のない堂々とした布陣であった。
「敵の数が判らないときや、少数の場合、もてる現有戦力すべてを出して、短期的に戦闘を終わらせるべきだ。戦力の逐次投入は、戦闘を長引かせるだけでなく、いらぬ損害を出す危険もある。しかし、この場合……」
タイラー艦隊の幕僚補佐を務めるエンリーク・ソロ大佐には不安があった。最初、クレティナス艦隊を視界に捉えたとき、彼はタイラーの判断の正しさを確信した。しかし、数瞬後、彼の思考は一八○度転換した。
「もしも、あの艦隊が囮だとしたら」
帝国軍とクレティナス軍の両者の相対距離は、開戦後三○分にして変化はなかった。二○光秒という距離を保ったまま、帝国軍が前進すればクレティナス軍は後退し、帝国軍が後退すればクレティナス軍は前進した。両軍の間には、艦隊から発射された長距離ビームや長射程の核融合弾が激しく交錯していたが、互いに損害は極めて軽微であった。
「これは、罠だ。クレティナス軍は戦力をこちらに集中させておいて、別働隊か何かが、防衛網の薄くなった要塞を直接攻撃するつもりだ」
エンリーク・ソロが叫んだと同時に、神将タイラーも考えていた。帝国艦隊は「バルディアスの門」より隔てること240光秒、二時間の距離にあった。もし、要塞に何かあれば、すぐにとって返せる距離である。しかし、明らかに時間かせぎとわかる戦法を取るクレティナス軍を見ると、彼らの意図がどこか別のところにあるのではないかと考えさせられるのだった。
「援軍を待つのだったら、わざわざ、ここまで出てくるはずはない。奴らの動きは明らかに陽動だ。私の知らないところで、別の何かが動いている」
第七艦隊旗艦「ビルスクニール(雷神の館)」の指揮官席に身をうずめて、タイラーは鋭い眼光を放つ紫水晶色の瞳を細めた。
両軍が暗黙の合意をしたかのように布陣して始まった戦いは、実につまらないものだった。互いの攻撃は相手に致命傷を与えることができず、慢性的な長距離砲撃戦が続く。
「これでは、埒があかん」
「どうなさいます、司令官閣下」
副官のアイスマン大佐が尋ねる。
「敵の別働隊が来るまで待ってやる理由もないな。仕方ないが、艦隊を分けることにしよう。敵を一気に片付ける。大佐、一九艦隊のラルツ中将を呼び出してくれ。提督に敵の側面に回り込んでもらう」
数瞬おいて、第一九艦隊の司令官オーエン・ラルツ中将が通信パネルに姿を現した。
「提督。すみませんが、第一九艦隊で敵の側面に回っていただけませんか。このままでは埒があきませんので」
「承知した。わしもそう思っておったところじゃ。敵も何か企んでいようが、その前に倒してくれるわ」
口を大きく開いて笑い声をあげた老提督にタイラーは頭をさげた。
「たのみます」
帝国軍第一九艦隊六五○隻は迂回を始めた。第七艦隊七五○隻は依然クレティナス軍と長距離戦を繰り広げている。だが、時間は刻一刻と時を刻んでいた。
「帝国艦隊が二手に分離したようです。おそらく、我が軍の側面か背後に迂回して挟撃するものと思われますが」
クレティナス軍、第四九艦隊司令官アルフリート・クライン中将は、戦艦「飛龍」艦橋の指揮官席に座して、平然と構えている。神将と呼ばれる男を前にして、彼には緊張がない。体温の上昇が多少はあったが、精神は落ち着いていた。
「ようやく、敵も焦れて動きだしたということか。さあて、こちらはどう対処したものかな」
「時間的には、あと四時間ほど粘ればよろしいと思いますが」
作戦時間の進行に合わせた時計に視線を投じて、ファン・ラープが応える。
ベルソリック、グエンカラー、ブラゼッティ等が率いる四九艦隊の別働隊が、小惑星を伴って「バルディアスの門」に到着するまで、まだ四時間が必要だった。いくらワープ可能な推進装置を備え付けているとはいえ、直接小惑星を、要塞との至近距離にワープアウトさせることはできない。技術的に問題がある上に、失敗すれば時空崩壊を招く恐れもあるのである。ゆえに、小惑星のワープアウト地点は「バルディアスの門」からある程度の距離を置いた宙域だった。
「四時間か。この状態をそこまで維持するのは難しいな。仮にも、私が相手をしているのは神将と呼ばれる男だ。簡単に済ませてくれるはずがあるまい」
艦橋の全天空スクリーンには、はるか前方で繰り広げられている長距離砲戦の閃光が、前衛芸術のように映し出されていた。クレティナス軍の繰り出す光の剣と帝国軍の光の剣が激しい火花を散らして交錯する。直撃を受ければ金属さえも沸騰させる熱量である。外の戦いは単調に繰り返され、エネルギーの無駄な消費が続く。
とはいえ、それに携わる人間の死傷率は、至近距離で砲撃戦を繰り返す通常の戦闘に比して著しく低い。一般の将兵達にとって、激しい戦闘による短期的な戦いと、単調な戦闘による長期的な戦い、どちらが好ましいものであろうか。
しかし、彼らの心情に関係なく、判断は降されるのである。クレティナス軍全将兵の生命を預かる赤毛の若き司令官は、前者を選択した。
「艦隊を再編。円錐陣をとる」
「突入されるつもりですか?」
ラッキー・ファンの顔が一瞬こわばる。
「ああ。すでに敵も部隊を二分した。これ以上、同じ戦い方をしていても、こちらが墓穴を掘るだけだ。短期的に勝敗を決しようと言うのではないが、ここは少し、タイラーに私の戦い方を披露してやろう」
アルフリートは理性的には戦争を嫌ったが、本能的には艦隊を指揮して知謀を競わせる戦いを好んだ。彼は戦争という名の殺人行為が、人道に反した人類最大の悪業だということを知っている。だが同時に、彼は武人でもあった。幾多の名将を相手に、ただの一度の敗北もない男を前にして、アルフリートの心は熱く燃えたった。
クレティナス第四九艦隊は、タイラー率いる帝国第七艦隊との相対距離を20光秒に保ったまま、陣形を凸形陣から円錐陣に再編する。そして、数分後、帝国軍が後退する瞬間をねらって、突然、前進を始めた。
|
 |
  |
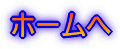
|

